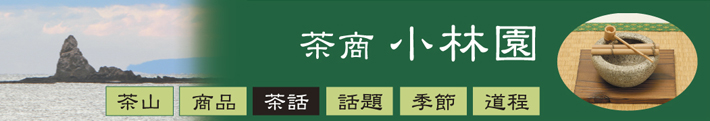
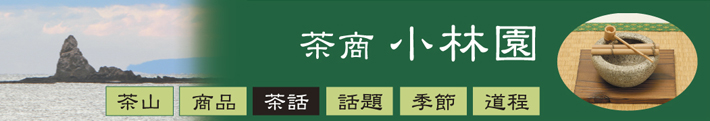 |
|
|
||||||
 |
| 宵越しのお茶は飲むな | |
|
前の日にお茶を飲んで、そのまま急須に残っている茶葉で入れたお茶というのは体によくない成分をもっているのです。お茶にはタンパク質が含まれており、長い時間気温の高いところに置いておくとカビが発生したり、細菌が増加して腐敗する場合があるのです。また、宵越しのお茶の中には濃くタンニンが抽出され、胃をこわすことも考えられるのです。
|
|
| お茶をにごす | |
|
一時しのぎに、その場をごまかしてつくろうこと。
|
|
| 茶々を入れる | |
|
じゃまをする、ひやかしてさまたげるという意味。
|
|
| お茶の子さいさい | |
|
「簡単」という意味で使われています。茶の子とはごく簡単な食事を表しており、腹が減っては戦ができぬ 、と反対で、茶の子程度で出来るという意味をもちます。「さいさい」とは語呂をよくするための一種の囃子であるようです。
|
|
| お茶に酔ったふり | |
|
酒も飲んでいないのに、酔ったふりをしてごまかすことの例えから、知っていることでも知らないふりをすること。
|
|
| 茶で墨をするな | |
|
お葬式の場合に茶の煎汁で墨をするならわしがあるので、平常時には茶汁ですった墨で文字を書くことは縁起が悪いと嫌った。また、「茶を硯水に使うと遺書になる」といって硯には湯茶をいれません。
|
|
| 日常茶飯事 | |
|
「日常」は普段という意。「茶飯事」とはお茶を飲んだり、食事をすること。つまり何のこともない、ごく普通 の行為というような意味。
|
|
| その口へ茶を飲むな | |
|
そのことばを発した同じ口で、平気な顔をして茶を飲むな、という意味。というわけで、「白々しいことを言うな」と同じ意味。
|
|
| 茶柱が立つと縁起が良い | |
| お茶に茶柱が立つと「何か良いことがある」と縁起をかついだ。これは全国的な吉凶習慣として知られています。人に話さないで黙っていると良いことがあると言われており、朝の茶柱は自分のもの、昼以降では他人のものとも言われる。 茶碗の真ん中に直立する茶柱が最も良く、待ち人などが必ず来ると言われました。 |
|